電磁石について
電磁石(electromagnet)とは、その名の通り電気的に作る磁石のことです。
電流を通電すると磁界が発生し、その中の鉄心が磁化されて磁石のような働きをするものを「電磁石」と呼びます。
電流を遮断すると磁界は発生しなくなり、ただの鉄芯に戻ります。
(実際には0(ゼロ)にはならず、鉄芯には僅かに残留磁気が残ります。
この磁力を実用に支障のない範囲まで打ち消すため、電源側で逆励磁回路や消磁回路等の工夫します)
電磁石の原理
銅線に電流を流すと、流す方向にしたがって磁束が生まれます。
この銅線を丸く輪っか状にすると内側に磁界が発生します。
さらに銅線を丸くらせん状に巻くと、巻いた分だけ磁界の力が強くなります。
このように銅線をグルグルと何回も巻いたものを「コイル」といいます。
このコイルの中に鉄心を入れると鉄芯が磁化され、まるで磁石のように他の金属を吸着するようになります。
下図では鉄芯を一回巻いているだけですが、実際には何重にも銅線をらせん状に巻きます。
巻いた分だけ磁界の力が強くなるので、鉄心を覆う磁束も増え、鉄芯はより一層磁化され金属を吸い付ける力も強くなります。
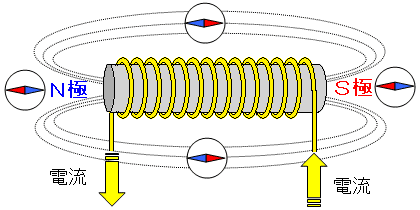
電磁石のメリット・デメリット
電磁石は電流を流している間だけ磁石になるので制御することが容易です。
電気を流す量を変えることで磁力の強弱をつけたり、流す向きを変えることで磁極を反対にすることができます。
また永久磁石に比べて莫大な磁力を得ることができます。
ちなみに医療用の一般的なMRIでは0.5T〜1.5T(5,000〜15,000ガウス)の超伝導電磁石が用いられ、
爆薬を使った磁場爆縮コイルなどは100T(1,000,000ガウス)超のものも存在します。
欠点は、電気が無くては磁石にならないため、電気を流し続ける必要があります。
電磁石を強くするには
電磁石の強さは、 電流の大きさとコイルの巻数に比例します。
おおざっばに言えば、電流が大きいか巻数が多ければ発生する力は強くなります。
ですが、この電流と巻数は互いに関係していて一方だけを都合よく増やすことはできません。
また電流の大きさを大きくする=発熱量≒温度上昇が増えるため、最悪の場合コイル焼損につながります。
この温度上昇を押さえるためには電磁石のサイズを大きくすれば良いのですが、機器のスペースが限られています。
このようにコイル設計では、 電磁力と発熱量の絶妙なバランスをとるような、 長年蓄積された経験が必要となります。
直流電磁石と交流電磁石
電磁石には直流電磁石と交流電磁石があります。
一般に私達の手もとに供給される電力は交流なので、電磁石もできるだけ交流を用いた方が便利です。
ですから、電磁接触器や継電器などの小型のものは、ほとんど交流電磁石を利用しています。
しかし、マグネット応用機器のような、大容量で使用頻度の高いもの、特別な形状のものなどには、
直流電磁石の方が向いています。
直流・交流電磁石の相違
| 相違部分 | 直流電磁石 | 交流電磁石 |
| コイル鉄心 | 鋳鋼、鍛鋼、軟鋼板等による塊状鉄心を使用。 | ケイ素鋼板を成層したものを使用。 |
| 始動電流 | 一定のコイル抵抗のみで定まるため、安定している。 | 始動時に非常に大きい電流が流れるため、電源にあたえる衝撃が大きい。頻繁に始動を繰り返すと焼損の危険がある。 |
| 唸り | 唸りは生じない。 | 磁束交番による吸引力脈動の唸りを生ずる。 |
| 機械的強度 | 強い。 | 成層構造を要するため劣る。 |
| 動作時間 | コイルのリアクタンスのために電流の確定に時間がかかるため、通電から吸引開始時間までに若干の遅れがある。 | 即応答性がある。 |